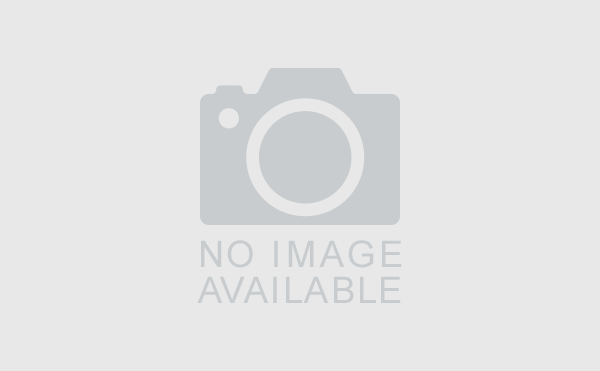習字の歴史
私が習字を始めたのは小学5年生のときでした。
父に連れられて、沖縄県うるま市にある、父が通っていたおじいちゃん先生のもとで習い始めました。
私、父、そして弟の3人で、日曜日のお昼に通っていました。
父はその時間にいろいろな話をするのが楽しかったのかもしれません。
習字のお稽古は少し退屈に感じることもありましたが、いつも先生に褒められていました。
賞もいただき、特に「観峰賞」をとることがモチベーションとなっていました。
中学に入ると、日曜日は友達との交流や部活動で忙しくなり、習字をやめることにしました。
それからしばらく習字とは離れていましたが、高校時代、
友人が家の近くの習字教室に通い始めたのをきっかけに、私も再び習字を始めることになりました。
最初はお花のお稽古から始め、その先生が習字も教えていると知り、習字を再開しました。
小学時代の先生は何枚も何枚も書かせるスタイルでしたが、高校時代の先生は楷書3枚、
行書5枚など、枚数を決めて書き、後から添削してもらうスタイルでした。
また、ペン字も学びましたが、思うようには上達しませんでした。
その先生の教室は自宅とつながっており、子どもたちの声が聞こえたり、
夕食を作りながら教室を運営している姿を見ることができ、とても憧れました。
それが、将来自宅で教室を開きたいという目標につながりました。
結婚して子供を出産するために一時期習字から離れましたが、その後再び習字を始めました。
そして、自宅で学研も始めたことをきっかけに、習字も教えることになりました。
最初は初段という実力不足で自信もありませんでしたが、「お金を稼ぎたい」という動機で頑張りました。
アパートで教室を始め、当時2歳の子供を連れて教室を運営し、
楽しく通ってもらえるようにさまざまな工夫をしました。
その後、マイホームを建てた際に敷地内に習字教室を作りました。
しかし、実績がない中で理想的な教室の大きさにはできず、教室を広げるために貯金を重ね、
ついに目標としていたトイレ設置と十分な広さを実現しました。
教室を開設した当初は、子どもたちに合わせて土曜日に教室を開き、午前中にお稽古、
昼にカレーライスを食べ、午後はみんなで遊ぶといった学童的な活動を取り入れて生徒を集めました。
生徒の親には友達やママ友が多く、彼女たちの支えも大きな力になりました。
また、生徒を増やすためにさまざまな工夫をしました。
ママ友にモニターになってもらったり、「あめ玉作戦」として出席者にプレゼントを用意したり、
毎月行事を企画していました。それはまるで学童のような教室運営でした。
さらに、散歩がてらチラシを配布したり、英語教室を開設して相乗効果を生み出したりと、工夫を重ねました。
はじめは自信がなかったので子供だけを対象としていましたが、
そのうち親子で通いたいという声が出てきたため、それを受け入れることにしました。
その後、地域でコミュニティを立ち上げ、その活動を通じて自然な流れで習字に入会する方も増えました。
今では大人が半分、子どもが半分という構成で、生徒数は60名近くにまで増え、
えつこ教室として多くの方に親しまれています。
トラブルもありましたが、それを乗り越えながら楽しく教室を運営してきました。
常に次のステップを考え、実践することで教室は成長を続けています。